良い投資先とそうでない企業はどこで峻別されるのかを理解するうえで、「経済的な堀(economic moat)」という概念を理解することは重要といえます。
千年投資の公理/パット・ドーシー (著)はこの分野の名著とされており、とても参考になりました。
出展:amazon
優れた製品=堀とは限らない
優れた製品は一時的な収益をもたらしますが、経済的な堀となることは多くありません。
たとえば、米国クライスラーが1980年代にミニバンを発売して大きな利益を得た事例は有名ですが、それが永続的な競争優位に直結したかといえば、必ずしもそうではありません。
現代においても短期的なブームで終わる製品は少なくありません。むしろほとんどがそうでしょう。もっとも、数か月単位の短期〜中期投資という観点では、こうしたテーマ性のある製品に着目することも戦略のひとつといえます。
経済的な堀の種類について
① ブランド・特許・行政認可による堀
たとえば、ティファニーは、同じ原価の宝石であっても“ティファニーブルー”の箱に入れることで高い価格設定が可能です。ブランド力が競争優位の源泉となる典型例といえます。
同様に、フェラーリ(RACE) や ウォルト・ディズニー(DIS) も、圧倒的なブランドによって価格競争に巻き込まれにくい構造を持っています。
日本株で言えば、サンリオ(8136) や 任天堂(7974) などもキャラクター商標やゲームIP(知的財産)によって、高収益性と競争優位を確立しているといえます。
行政認可の例としては、ムーディーズ(MCO) や S&Pグローバル(SPGI)、さらに日本では 日本取引所グループ(8697) などの金融業界の企業が挙げられます。特定の業務には国家・行政の許認可が必要であり、新規参入のハードルが非常に高いといえます。
さらに、小型株であっても、ごみ処理業者や火葬場など、地域行政からの認可が不可欠な事業も、堀として機能する場合があります。
ただし、行政認可があるからといって、必ずしも効率的なビジネスが行われているとは限らず、個別に精査する必要があります。
② 乗り換えコストによる堀
顧客が他社製品やサービスに乗り換える際に高コストが発生する場合、その企業は顧客を囲い込む堀を形成しています。
たとえば、マイクロソフト(MSFT) のOfficeやAzureのように、多くの企業に導入されているシステムは、他社への乗り換えに多大な教育・運用コストがかかります。多くの会社員がofficeソフトを使用していると思いますが、いまから少し安くて使いやすいソフトに乗り換えるイメージは湧きづらいといえます。
分析機器メーカーや専門的なCADソフトウェアなどもこの枠に入ります。導入後の再教育、旧製品との整合性、データ互換性などがハードルとなるため、顧客の切り替えは容易ではありません。
③ ネットワーク効果による堀
ネットワーク効果とは、利用者が増えるほどサービスの価値が高まる構造です。これにより、先行企業が優位を築きやすくなります。
たとえば、Visa(V) や Mastercard(MA) は、加盟店・利用者のネットワークを拡大することで寡占状態を築いており、新規参入が困難なビジネスモデルとなっています。
また、メルカリ(4385) のようなCtoCマーケットプレイスは、利用者が多いため出品も豊富であり、さらに利用者が集まるという好循環を生んでいます。手数料の安い競合(PayPayフリマやラクマなど)があっても、シェアを維持しているのはネットワーク効果の賜物です。
同様に、CMEグループ(CME) は、金融取引所としてのネットワークと行政認可という2つの堀を組み合わせることで、競争優位を築いています。
先に挙げたMicrosoftのWordやExcelも事実上のデファクトスタンダードとして機能しており、これも強固なネットワーク効果に支えられています。
最後に:市場に過小評価されている“堀”を探す
たとえ経済的な堀を備えた優良企業を見つけたとしても、その価値がすでに市場に織り込まれている場合、割安とは言えません。
むしろ、先に挙げたような企業はすでに’経済的な堀’についても皆が認識して株価に織り込まれていることもしばしばあるため、注意が必要です。
最も魅力的な投資機会とは、市場がまだ十分に評価していない堀を見抜き、企業価値が適正に認識される前に投資することです。
このように、経済的な堀の存在を軸に企業を分析することは、長期的な視点で資産を築くうえで非常に有効です。今後も、単なる業績ではなく、構造的な競争優位性に注目することが、賢明な投資判断につながると考えています。
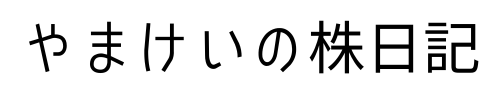
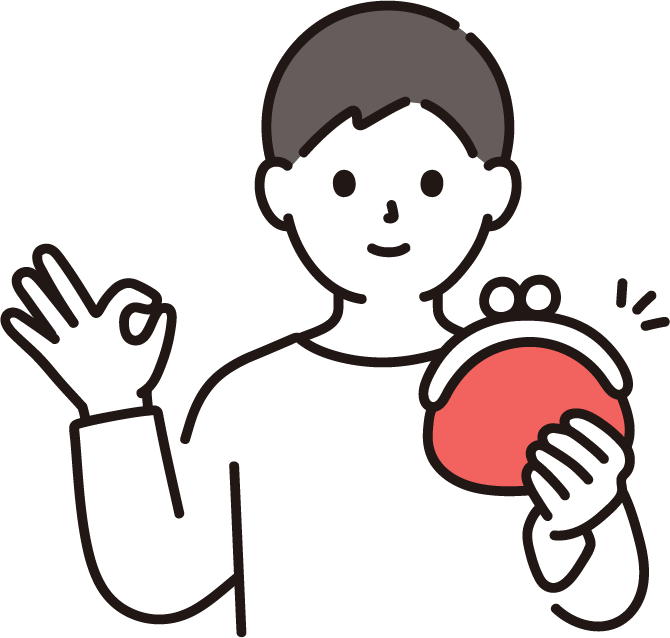
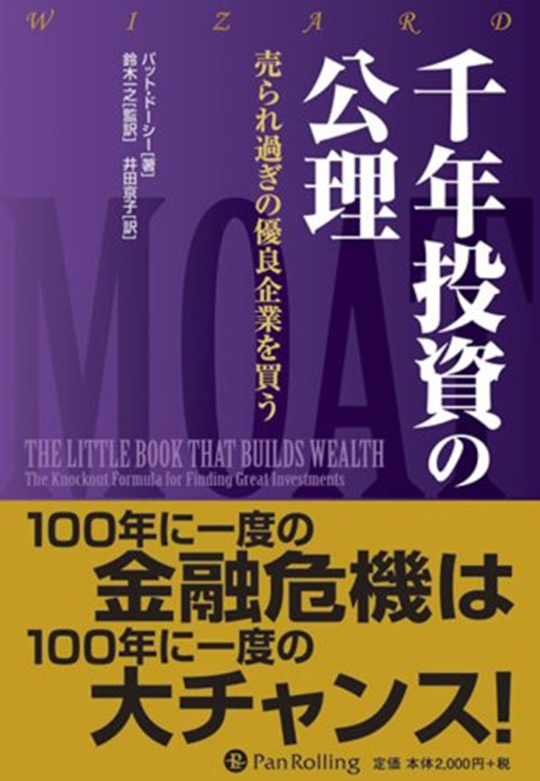

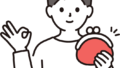
コメント